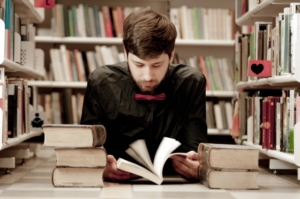
はじめに
「急坂の上の物件」は43条ただし書き物件です。
43条ただし書きは、接道義務を満たせず、本来家を建てることが出来ない土地において、例外的に家の建築を認めるものです。
そのため、家の建築を認めてもらうためには、いくつかクリアーしなければならない条件があります。
小林住宅工業(こばじゅう)に任せっきりでしたので、自身でも何をやる必要があるのか?きちんと理解しておこうと思います。
まずはおさらい。43条ただし書きとは?
建築基準法第四十三条 建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
とあるように、道路に2メートル以上接していなくとも例外的に建築審査会の同意を得れば家を建ててもいいですよ。
という内容になっています。
クリアーすべき2つの基準
神奈川県には43条ただし書きの許可において、「建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可基準」と「建築基準法第 43 条第1項ただし書の規定による許可に係る包括同意基準」の2つの基準があります。
「建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可基準」は43条ただし書きの許可に際して、神奈川県が建築審査会に出す前に、許可相当とするか否かを定めたものです。
「建築基準法第 43 条第1項ただし書の規定による許可に係る包括同意基準」は、建築審査会の審査において、手続き簡略化のため、この基準に基づいてなされた許可については審査せずに許可に同意しますという内容です。
建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可基準
我が家に関係しそうな部分を抜き出すと下記になります。
かなりの内容ですね。
※特に対応を要する項目については太字にしています。
3 敷地が通路に接する場合の基準 計画建築物が、省令第 10 条の2第三号に適合する場合にあっては、次の(1)及び(2) の内容に適合していなければならない。
(1)省令第 10 条の2第三号に掲げる通路、計画建築物及びその敷地が、次に示す項目に すべて適合していること。
ア 通路は、通行に有効な範囲が明確であること。
イ 通路は、アの通行に有効な範囲内において、その上空に工作物が突き出したも のでないこと。
ウ 通路は、砂利敷きその他ぬかるみとならない構造であること。
エ 敷地の境界線は、通路の中心線からの水平距離2メートルの線であること。た だし、当該通路がその中心線からの水平距離2メートル未満でがけ地、川、線路 敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の通路の側 の境界線から通路の側に水平距離4メートルの線を敷地の境界線とし、また、(2) ウ(ア)に掲げる通路の拡幅整備に係る協定が締結された場合その他やむを得ない と認められる場合においては、協定に定めた位置又は別に知事が認めた位置の線 を敷地の境界線とする。
オ 敷地は、エの敷地の境界線を通路の境界線とみなし、その通路の境界線に2メ ートル以上接していること。
カ 計画建築物は、既存建築物の建て替え又は増築であること。ただし、新築で以 下のいずれかに該当するものはこの限りでない。なお、ここでいう既存建築物の 建て替えとは、従前からその敷地が当該通路に接していたもので、現に存する建 築物を除却し、新たな建築物を建築するものをいう。
(ア)既存建築物の敷地を分割することにより生じさせた土地に、新築するもの
(イ)従前に建築確認のなされた経緯の明らかな土地に、新築するもの
(ウ)平成 11 年4月 30 日まで建築物の敷地であったことが明らかな土地に、新築 するもの
(エ)通路沿道の他の既存建築物の敷地と、通路の利用実態が同等であると認めら れる土地に、新築するもの
(オ)法第43条の許可若しくは条例の許可に係る処分がなされた建築物の敷地であ った土地に、新築するもの
(カ)公益上必要な施設を新築する場合その他の場合で、計画建築物の立地上やむ を得ないと認められるものキ 通路の幅員が 1.8 メートル未満である場合、計画建築物は一戸建ての住宅又は 既存建築物と同じ用途であること。
ク 通路の幅員が4メートル未満である場合、計画建築物の地階を除く階数は2以 下であること。
ケ 計画建築物の外壁若しくはこれに類する部分から隣地境界線までの水平距離は、 消火活動等を考慮し、0.6 メートル以上有効に確保されていること。ただし、増築 の場合、当該増築部分以外の部分においては、この限りではない。
コ 計画建築物は、通路を法第 42 条に規定する道路とみなして法及び施行令の規定を適用した場合に、適合したものであること。なお、各規定の適用の方法につい ては、それぞれ以下のとおりとする。
(ア)通路の幅員が4メートル未満である場合は、原則として当該通路を法第 42 条 第2項の道路とみなして各規定を適用するものとし、その場合の境界線の位 置についてはエに示す内容による。ただし、次のaからcに掲げる規定につ いては、通路の部分のみを道路とみなして適用する。なお、(2)ウ(ア)に掲 げる通路の拡幅整備に係る協定が締結された場合におけるa及びbの適用に ついては、当該協定に定めた内容によることができる。 a 容積率の算定(法第 52 条第2項) b 道路斜線制限(法第 56 条第1項、第2項、第6項) c 採光計算(施行令第 20 条第2項)
(イ)通路の幅員が4メートル以上である場合は、当該通路を法第 42 条第1項に規 定する道路とみなして各規定を適用する。
(ウ)法第 56 条第7項第一号(天空率による斜線制限の適用除外)の規定は準用で きないものとする。サ 計画建築物が、都市計画法第 37 条第一号により建築制限の解除が認められたも のである場合は、その敷地が同法第 29 条の開発許可による整備予定の道路に2メ ートル以上有効に接するものであること。この場合においては、アからコまでの 基準及びシの基準は適用しないものとする。
シ 既存建築物の敷地が道路に 1.8 メートル以上2メートル未満の長さで接するも のにあっては、次の基準に適合していること。この場合においては、アからサま での基準は適用しないものとする。
(ア)計画建築物における避難可能な開口部から道路までの間、避難上有効な幅員 1.8 メートル以上の敷地内通路が確保されていること。
(イ)既存建築物の建て替え若しくは増築であること。
(ウ)既存建築物及びその敷地が、平成 11 年4月 30 日以前の状況と同様であるこ と。ス 計画建築物又はその敷地が、都市計画法など関連する法令若しくはそれらに基 づく条例の定めによる許認可を要する場合においては、それらの許認可が受けら れるものであること。
(2)省令第 10 条の2第三号に掲げる通路、計画建築物及びその敷地が、次の交通上、安 全上、防火上及び衛生上支障がないものとして必要な性能を示す項目に、すべて適 合していること。
(交通上支障がないこと)
ア 日常生活において歩行者(自転車等の軽車両を含む。以下同じ)が円滑に通行 できるものとして、次の基準に適合していること。
(ア)通路は、道路に接続するまでの間、歩行者が通行する上で十分な幅員が確保 されていること。
(イ)通路は、その沿道の建築状況を考慮し、現状の通行利用及び将来予測される 通行利用に適した構造であること。イ 自動車が通行する通路又は将来自動車が通行することが予測される通路(幅員 4メートル以上のものを除く)である場合は、緊急時に緊急車両が通行できるも のとして、次のいずれかの基準に適合していること。なお、ここでいう緊急車両 とは、消防関係車両、警察関係車両及びその他これらに類する車両を指すものと する。
(ア)敷地内に、一般車両の転回に有効な空地(計画建築物の利用者の用に供する 駐車場を除く。)が確保されていること。
(イ)敷地内に、緊急車両を通行させるため一般車両が一時的に待避することので きる空地(計画建築物の利用者の用に供する駐車場を除く。)が確保されてい ること。ただし、この空地は、当該待避時において通路の有効幅員が 2.5 メ ートル以上確保されるものに限る。
(ウ)通路は、一般車両の転回広場(建築物の敷地内に設けられたものを除く。)が 設けられたものであること。
(エ)通路は、その両端が道路に接続したもので、当該通路を一般車両が通り抜け ることにより緊急車両が滞りなく通行できるものであること。(安全上支障がないこと)
ウ 通路の通行利用時における安全性の確保並びに災害時における避難及び消防活 動に有効な空間の確保を目的とし、周囲の状況に応じ、次のいずれかの方法によ り、将来にわたり安定して通路の機能が維持されるものであること。
(ア)通路の沿道に、住宅その他の建築物(計画建築物を除く)の敷地が2以上あ る場合は、それら建築物の所有者、管理者又は占有者(建築物のない土地が ある場合はその土地の所有者)と申請者相互において、別に定める内容によ り、当該通路の拡幅整備に係る協定が締結されていること。
(イ)敷地が通路に接する部分から直近の道路に接続するまでにおける通路部分の 土地所有者等より、計画建築物の利用者の通行及び当該土地の通路としての 維持管理に係る同意が得られていること。ただし、道路法による道路の部分 についてはこの限りでない。エ 効果的な消防活動を促進するものとして、次の(ア)から(ウ)の基準に適合して いること。
(ア)通路は、消防関係車両が通行するための十分な幅員が確保されること。ただ し、幅員その他の構造上の理由により消防関係車両が通行できない通路であ る場合は、消火活動に関し消防本部等との必要な調整がなされ、消防活動に 概ね支障が無いものであることが確認されたものであること。
(イ)計画建築物の周囲に、消火活動に有効な空地(敷地内のものに限る)を有す るものであること。ただし、計画建築物が耐火建築物若しくは準耐火建築物 (主要構造部が準耐火構造であるものに限る)である場合にあってはこの限 りでない。
(ウ)計画建築物が3階以上の階を有する場合、非常用進入口若しくはそれに代わ る進入口の位置は、通路から明確に視認できること。オ 計画建築物の利用者が短時間で安全に避難できるものとして、次の(ア)及び (イ)の基準並びに(ウ)から (オ)のいずれかの基準に適合していること。
(ア)計画建築物における主要な出口から通路に至るまで、滞りなく安全に避難で きること。
(イ)通路は、道路に至るための避難上主要な経路となるものであること。
(ウ)敷地内に、計画建築物の利用者の一時的な待避に有効な空地が確保されてい ること。
(エ)(イ)の主要な経路となる通路の他に、道路に接続する他の通路が存すること。
(オ)通路は、避難するための十分な幅員が確保され、かつ道路に至るまで、滞り なく安全に避難できること。(防火上支障がないこと)
カ 隣接建築物からの延焼及び隣接建築物への延焼を防止できるものとして、次の 基準に適合していること。
(ア)計画建築物の配置計画及び平面計画は、隣接地など周囲の建築状況を考慮し、 適切であること。
(イ)計画建築物の外壁及び軒裏は、防火地域等の指定若しくは周囲の建築状況を 考慮し、適切な防火性能等を有するものであること。ただし、延焼のおそれ のある部分に計画建築物が存しない場合は、この限りでない。
(ウ)計画建築物の屋根その他これに類するものは、防火地域等の指定若しくは周 囲の建築状況を考慮し適切な構造であること。
(エ)計画建築物の開口部は、防火地域等の指定若しくは周囲の建築状況を考慮し、 適切な遮炎性能を有するものであること。(衛生上支障がないこと)
キ 各居室の開口部について、道路に面する場合と同等の採光・通風性能が得られ るものとして、次の基準に適合していること。
(ア)計画建築物の居室で、その開口部が通路にのみ面している場合は、通路から 当該開口部までの距離が十分に確保されていること。
(イ)隣地境界線からの水平距離が、十分に確保されていること。ク 汚水、雨水等の排水が敷地外に適切に排水されるものとして、次の基準に適合 していること。
(ア)敷地内に適切な排水施設又は処理施設が設置されていること。
(イ)敷地内の排水施設又は処理施設から敷地外の排水施設に、有効に接続されて いること。ただし、敷地内において適切に浸透処理される場合を除く。
この中でやるべきことは、特に下記の4つと言えそうです。
- 土地の境界から家までは0.6メートル以上離す
- 家を建てる際には私道の地権者から利用に関する同意を得る
※我が家も4分の1の権利を有しますが、残り4分の3の地権者への同意が必要なようです - 消火活動に有効な空地を設ける
※ただし基準は明確でないようです。 - 適切な防火性能を設ける
※これは準防火地域相当の対応が必要となります。
建築基準法第 43 条第1項ただし書の規定による許可に係る包括同意基準
我が家に関係しそうな部分を抜き出すと下記になります。
※特に対応を要する項目については太字にしています。
(2) 通路が道路に接続する部分まで幅員4メートル以上の法第 42 条第1項各号に該当しな い道である場合にあっては、計画建築物の用途、規模、構造、敷地及び通路が以下の基準を満たしているもの
ア 敷地が当該通路に2メートル以上有効に接していること
イ 計画建築物における避難可能な開口部から当該通路に有効に接する部分までの間、有効幅員 1.5 メートル以上の敷地内通路が確保されていること
ウ 敷地が通路に接する部分から直近にある道路に接続する部分までの当該通路の土地の所有者より、計画建築物の使用者及び利用者の通行並びに当該通路の維持管理に係る同意が得られていること
エ 計画建築物は、通路を法第 42 条第1項に規定する道路とみなして法及び施行令の規定を適用した場合に、適合したものであること
オ 通路は砂利敷きその他ぬかるみとならない構造とし、通路部分の境界がコンクリー ト境界石等で明示されているものであること
カ 計画建築物の用途、規模及び構造が次のとおりであること
・計画建築物の用途が住宅、長屋、下宿、共同住宅、寄宿舎、店舗・事務所併用住宅 (第1種低層住居専用地域内に建築することができるものに限る)又は診療所であ ること
・高さが 10 メートル以下であること
・延べ面積の合計が 200 平方メートル以下であること
・階数(地階がある場合は地下1階を除く)が2以下であること
・長屋及び共同住宅にあっては戸数が2以下、下宿の宿泊室及び寄宿舎の寝室にあっ ては室数が2以下であること
この中でやるべきことは、特に下記の2つと言えそうです。
- 家と建てるときに、玄関から敷地外までは幅が1.5メートル以上の通路を設ける
- 家を建てる際には私道の地権者から利用に関する同意を得る
※我が家も4分の1の権利を有しますが、残り4分の3の地権者への同意が必要なようです
まとめ
「急坂の上の物件」が43条ただし書き物件であるため、43条ただし書き許可を得るために何が必要かを調べてみました。
様々ありましたが、特に下記の点が必要なようです。
- 土地の境界から家までは0.6メートル以上離す
- 家を建てる際には私道の地権者から利用に関する同意を得る
- 消火活動に有効な空地を設ける
- 適切な防火性能を設ける(準防火地域相当の対応)
- 家と建てるときに、玄関から敷地が今では幅が1.5メートル以上の通路を設ける